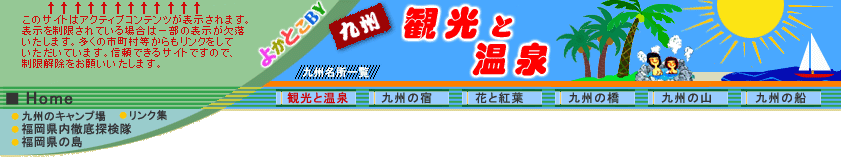
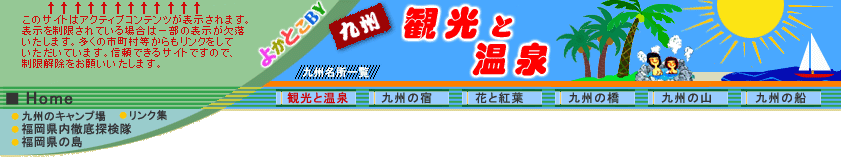
| 天念寺の修正鬼会 ( しゅじょうおにえ ) |
|
|
◆ 【15:03頃】 僧侶が盛装(せいそう)姿でやって来た ※ 2011/02/09 撮影 
◆ 【18:13頃】 川中不動の周辺に松明(たいまつ)が灯された 
◆ 【20:05頃】 講堂前で大松明(おおだい)を左右に三回振り、上下に三回振る (三々九度の法による「献灯の儀」)  ◆ 講堂前で大松明(おおだい)をぶつける (大松明の火合わせ) 
◆ 【21:56頃】 僧侶が口に含んだ水を吹きかけると両手に小松明(こだい)と斧を持って「鬼招き」が始まる  ◆ 本介錯と鬼役の僧侶が一緒に飛んだり跳ねたりして呼吸を合わせ鬼招きを行い、呼吸があうと鬼が僧侶に乗り移る  ◆ 鬼は御先祖様の化身らしい。角が無く耳が大きいのが特徴  ◆ 【22:07頃】 黒鬼(荒鬼)が作られる  ◆ 僧侶が口に含んだ水を吹きかけると黒鬼(荒鬼)が誕生する  ◆ 黒鬼(荒鬼)が講堂のニワ(回廊)をあばれ回る  ◆ 鬼になっているのは僧侶です  ◆ 【22:20頃】 赤鬼と黒鬼のコラボ  ◆ 赤鬼と黒鬼はポーズをとってくれる  ◆ 赤鬼と黒鬼は松明を頭上で交差してグルグル回る  ◆ 鬼の目 餅撒(もちまき)。鬼の目餅と呼ばれる2枚の鏡餅がまかれ、群衆が殺到し、鬼は餅を拾った人を追いかけ回す  ◆ 【22:28頃】 見物客は鬼に肩や背中を叩いてもらい無病息災の加持祈祷(かじきとう)を受ける  ◆ タイレシ(松明入れ衆)も鬼に叩いてもらい無病息災の加持祈祷(かじきとう)を受ける  ◆ 最後にもう一度ポーズをとる  ◆ 【22:44頃】 また、鬼の目 餅撒(もちまき)があり、観客は餅を奪い合う。 鬼が二匹なので餅撒(もちまき)も2回かな?  ◆ 【22:47頃】 本介錯(ほんかいしゃく)に背負われて鬼が退場する  ◆ 【22:49頃】 最後に餅まきが行われる 
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||